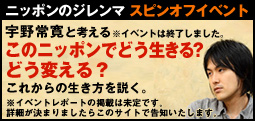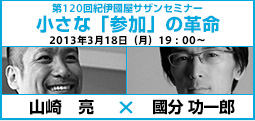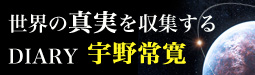情報分析の世界とはどういうものか――インテリジェンスに関するジレンマ【第2回】:小谷 賢
今年のはじめに起こったアルジェリアの人質事件は、日本政府の危機管理に対する様々な問題点を浮かび上がらせました。安倍政権のもとで日本版NSC(国家安全保障会議)の創設に対する気運が高まるなか、はたして国家や組織は情報をいかにして扱うべきなのでしょうか。インテリジェンスに関するホットな議論を、情報史の第一人者である小谷賢さんに解説していただきます。
小谷 賢 (コタニ・ケン)
1973年、京都府生まれ。防衛省防衛研究所戦史研究センター主任研究官。専門は、イギリス政治外交史、インテリジェンス研究。著書に『イギリスの情報外交 インテリジェンスとは何か』(PHP新書)、『インテリジェンス 国家・組織は情報をいかに扱うべきか』(ちくま学芸文庫)、『日本軍のインテリジェンス なぜ情報が活かされないのか』(講談社選書メチエ)など。
■日本にとっての情報分析
前回、対外情報機関とは情報を収集し、質の高い情報を持つことで各国の情報機関と世界中の情報を交換するためのものであると書いた。収集については前回紹介した人的な情報収集のほかにも、衛星で地上を撮影したり、通信を傍受したりといろいろなやり方がある。しかし実は各国の情報機関が集める情報の90~95%ぐらいは、新聞やインターネットなどから得られる公開情報なのである。つまり情報機関とはごく特殊な情報源を除くと、世界中の公開情報を基本としているので、公開情報の選別や分析の技術に長けた組織だといえる。そのため、情報分析の能力を上げることでも質の高い情報を持つことは可能なのである。
ところでこの間、欧米の元情報関係者から日本のインテリジェンスに関するアドヴァイスをいただいた。それは日本がいきなり米国中央情報庁(CIA)や英国秘密情報部(MI6)のような機関を設置するのはとても無理なので、とりあえずは情報分析能力を強化すべきではないかというものであった。恐らくこの点で先例となるのは、CIAの前身となったアメリカの戦略事務局(OSS)なのだろう。1940年代のアメリカでは既に軍部と連合捜査局(FBI)がインテリジェンスを牛耳っていたため、そこに新規の対外情報機関を設置するというのは大変なことであった。そのため最初に設置されたのは、情報分析を専門とするOSSだったのである。
OSSは第二次大戦中にアメリカの情報機関として設置された組織だが、その任務は情報収集から分析、また宣伝工作まで幅広いものであったという。有名な調査分析部門(Research&Analysis)には、著名な歴史学者のアーサー・シュレジンジャーJr.やウィリアム・ランガー、経済学者のウォルト・ロストウら当時の一級の学者が集められ、ジョン・フォードのような映画監督もOSSに協力しており、OSSは情報機関でありながら、優秀なシンクタンクのようであったと言われている。
なので日本でもいきなり対外情報収集というよりは、各省庁や研究機関が知恵を出し合って公開情報からでも有益な情報を生み出すことのできる、分析に特化した組織を設置してみるのも手であろう。実のところ、日本人が世界中に出かけていって法律すれすれの情報収集を行うよりは、地道に情報分析を行うほうが向いているのではないか。
現状、日本の官公庁の組織には国全体の情報分析に特化した組織はあまり見当たらない。恐らく内閣情報調査室の分析官制度ぐらいであろう。この組織は各省庁からの情報を総合的に分析しているといわれているが、わずか6人で国の情報を分析しているのだ。少数精鋭といわれるイギリスでも40人の規模で分析をやっていることを考えると、日本の規模は超少数だろう。
このように日本にとって、情報分析の領域はまだまだフロンティアでもある。分析官に必要な人材は、語学や地域情勢に明るく、データマイニングなど統計解析の技術にも長けていることが望ましい。そのような人材は霞が関のみならず、民間企業やアカデミアにも必ずいよう。分析能力を高めれば、情報の質は必ず上がるのである。
■情報と目的
最近出版された『知の逆転』という本の中で、かのノーム・チョムスキー氏が「垂れ流しの情報があってもそれは情報がないのと変わりません。何を探すべきか知っている必要がある。」(102頁)と述べているが、まさにこれは情報の洪水の中で日々我々が直面している状況だ。基本的に情報機関は、政治家や軍人の必要に応じて情報を収集し、分析するため、「自分が何を知りたいのか、何を探すべきなのか」については大よそわかっている。なので情報の洪水でおぼれることはそうない。
太平洋戦争中の日本軍は米軍の情報を集めるべく、藁をもすがる思いでアメリカの新聞や雑誌などを買い集めていた。これらの情報を分析していた日本陸軍の堀栄三大佐は、アメリカの缶詰会社と製薬会社の株が上がると、それに続いて米軍の大規模作戦が行われるということに気がついた。またキューバのフィデル・カストロ議長の健康状態を何としても知りたかったCIAの分析官たちはテレビ映像を見続け、議長が透析と人工肛門に頼っているという分析結果を導き出した。つまり情報収集と分析の目的がはっきりしていれば、公開情報もばかにはならないということだ。
むしろ問題は情報を利用する側である。政治家から「A国はどうなるのか?」と漠然とした質問をされても、情報機関のほうはどんな情報を集めて提示すればよいのか戸惑うだろう。しかし「A国の指導者がこのような声明を発表したが、その背景を知りたい」という明確な要求を出せば、情報機関としても何を集めてどう分析すればよいか見当がつくのである。このように目的が明確化すればするほど、分析対象も絞られていくので、情報を要求し、利用する側は、常に世界情勢や戦略について考えておく必要がある。
例えばジョン・F・ケネディ大統領は、人類初の月面上陸計画の初期の段階で、どうすれば計画を成功させられるのか、かなり細部まで検討していたという。1963年にリンドン・ジョンソン副大統領に宛てた手紙には、「宇宙に実験室を打ち上げるか、ロケットで月を周回させるか、飛行士を載せたロケットを月に着陸させて帰還させるか、いずれかの手段でソ連との競争に勝てる可能性はあるか。そのためには追加費用はどのくらいかかるか。現在の計画に全力で取り組んでいるのか。取り組んでいないならそれはどうしてか。本気でやればどのぐらいペースを上げることができるのか。」と事細かい注文が書かれていた。事務方はこれらすべてに回答し、それに納得したケネディ大統領は、月面上陸を本格始動させたのである。
情報収集の目的や分析の対象が明確になって初めて、情報収集やデータマイニングの作業は効率よく行えるようになる。よく官公庁や企業の会議室でデータをきれいに纏めた円グラフなどを目にする機会があるが、データを纏めるという手段が目的となってしまっている場合、そのデータから何がわかるのか、何が言いたいのかがはっきり伝わってこない。問題は分析の目的が明確化されていないからだ。目的を明確にしようとすれば、常に対象への考えを巡らせておかなければならない。この思考段階を飛ばしてしまうと、情報の洪水におぼれ、情報の分析などとてもできなくなる。
『マネーボール』という映画では、弱小球団のスカウトがお金をかけずにどうすれば勝つことができるか、ということを考え続け、最終的に野球はアウトにならない限り、負けることはない、そのためには比較的年俸が安くて出塁率の高い選手を獲得すればよい、という結論を導き出したのである。出塁率に注目さえしてしまえば、野球にまつわる膨大なデータから何を探せばよいのかはっきりするというわけだ。
■ラムズフェルドの「未知の未知」
情報とは取ってきたものがそのまま使えるということは稀なので、まずは使う目的のためにカスタマイズする必要がある。そして自分の調べる対象が、どのようなものであるか知っておく必要がある。
2002年2月、アメリカではイラク侵攻の可能性について議論が白熱していたが、そのポイントはイラクが本当に大量破壊兵器を保持しているかどうかであった。この点について記者から質問を受けた当時のドナルド・ラムズフェルド国防長官は、「我々の知らないことが存在することを我々は知っているが(未知の知)、我々が知らないということすら知らないことも存在している(未知の未知)」と禅問答のような回答をしたのである。
この言葉は記者の質問をはぐらかしているようにも思えるが、それはさておき、インテリジェンスの世界で「未知の知」と「未知の未知」の問題は区別されなければならない。前者はあることはわかっているが情報がないので推論や分析に頼らざるをえない領域、例えば冷戦期のソ連のミサイルの数や北朝鮮が保有している核兵器の数である。後者は果たしてあるのかないのかもわからないもの、これは例えば相手国の指導者が何を考えているのか、30年後の世界がどうなっているのか、といった事項であり、こういった分野はいくら分析をやっても明確な答えは得られないだろう。冷戦期にCIAはソ連の経済状況をこと細かく調べ上げ、それらは的を射たものであった。ところがソ連の崩壊ということまでは予測できなかったという。これは前者が「未知の知」にあたり、後者が「未知の未知」にあたるからである。
人間が「未知の未知」の領域に踏み込もうとすると大抵はロクなことにならない。人間の頭脳はすべての情報を処理して世界を俯瞰できるほど高度なものではないのだ。1910年代のヨーロッパでは世界は平和になる、といった言説がまことしやかに唱えられたが、1914年に未曽有の大戦争が勃発してヨーロッパは荒廃した。1960年代には世界的な食糧危機が起こるといわれたがそうはならず、1980年代には21世紀が日本の世紀になると予測された。最近ではリーマンショックの直前までアメリカの株高は当面続くと信じられていたほどだ。人間、特に専門家と言われる種類の人々ほどそれっぽい理論武装をし、「未知の未知」についてわかった風に話すが、そんなものは全く当てにならない。むしろ一般常識を持った普通の人々による集団知のほうがよほどマシだ。
他方、「未知の知」に切り込むにしても肝心の情報がなければどうしようもない。今年1月にアルジェリアで人質事件が起きた際、テレビや新聞などでコメンテーターが事件は長期化しそうだと話しているのを何度か耳にした。その理由としては、1997年に発生した在ペルー日本大使公邸占拠事件の際、ペルー当局の突入と解決までに4か月以上かかったことが挙げられていた。ところが大方の予想に反し、アルジェリア軍は事件発生から数日で突入作戦を敢行したのである。一見、ペルーの人質事件の際の対応というのはもっともらしい理由だが、これは理由になっていない。「ペルーではこうだったからアルジェリアでもこうではないか」というのは印象論にすぎないのである。我々はこの手の話に騙されがちであるが、この場合、現地の情報を十分に入手できていないと確実な情勢判断などできないのである。
このように情報分析の世界では、分析できる対象はごく限られている。情報がなければその対象はさらに狭まるのである。
■主観とのたたかい
先ほど、人間の脳は世界を俯瞰できるほど高度なものではないと書いた。その理由は人間の主観性に端を発する。我々はアルジェリアでの例のように根拠の薄い理由を挙げ、その上に主観的な推論を築き上げる。また人間は理性よりも直感を優先したり、判りやすい結論を好む。例えばルーレットで「赤→赤→赤→赤→赤」と出ていれば、次こそは黒に賭けたくなるのが心情というものであろうが、冷静に考えると赤と黒が出る確率は常に二分の一なのである。
さらに人間は最初に受け入れた情報の正誤に関わらず、それに縛られてしまう傾向もある。例えばトルコの人口について即答できる人は少ないだろうが、最初に「トルコの人口は3,000万人より上ですか、下ですか」という質問を投げかけられた後、改めてトルコの人口を尋ねてみると、多くの人が3,000万人前後の数を答えるという(答えは7,000万人)。
このように人間は曖昧な仮説から話を進め、また最初に受け入れた情報に縛られるという生き物なのだ。これに対して情報分析の世界では、なるべく主観の入る余地を排除しようとする様々な手法が採られている。その一つが競合仮説分析と呼ばれるもので、これは人間が情勢判断をする際、仮説の段階で間違ってしまうことを避けようとするものである。やり方を非常に簡単に説明すると、最初の段階で考えられる限りの仮説を幾つも立てておき、その後入手した情報と比較しながら、成り立たない仮説を排除していく。そうすると仮説の数は絞られ、誤った仮説の上に推論を立てることがある程度回避できるのである。
例えば1962年10月のキューバ危機の際、CIAにはソ連がキューバに核ミサイルを持ち込んだとする様々な情報が寄せられていた。ところがCIAの分析官の多数の意見は、「情報は間違いだ。なぜならソ連が核戦争の危険を冒してまでキューバにミサイルを運搬するはずがない」というものであった。これはソ連が核戦争のリスクを負うわけがないという、分析官たちの思い込みから生じた結論であったが、実際にソ連はミサイルをキューバに持ち込んでいたのである。もしこの時、競合仮説分析のようなやり方を用いていれば、分析官たちの意見は簡単に反駁されたはずだ。なぜなら競合仮説分析を用いた場合、「ソ連がキューバに核ミサイルを持ち込むはずがない」という前提は、すでに寄せられている様々な情報によって最初に否定されてしまうからである。
競合仮説分析をはじめとする分析手法は、人間の主観の介入を最小限にするという意味では有効である。ただしこれはあくまでも仮説の確度を上げるためのものであり、これだけでは分析作業は不十分である。インテリジェンスの世界で分析とは、データとデータを繋ぎ合わせ、最終的には報告書という形でストーリーを紡ぎ出す作業なのだ。
■アートと技術
私はお宝鑑定番組などをよく観るのだが、鑑定士の先生方は一応パフォーマンスのために骨董を調べる演技をしているが、ほとんどのものはぱっと見れば真贋の区別がつくのだそうだ。逆に我々素人は、骨董品の真贋を知ろうとすれば、品物の箱書きがあるかないか、書籍やネットに似たようなものがないかといろいろな方法で調べる必要がある。インテリジェンスの世界にも似たような話があって、熟練した分析官が「理由は上手く説明できないがこうだと思う」というような分析が当たったり、若手の分析官がいくら証拠を集めて分析しても上手くいかないことが多々ある。前者は右脳的なアートの領域であり、後者は左脳的な技術論である。
技術論については競合仮説分析のようなやり方が確立していることをすでに述べた。アートの部分は基本的には人ぞれぞれとしか言いようがないが、いずれにしても分析というのは技術とアートが必要になってくるのである。どうすればアートが身につくのかは学術的素養や経験論になってくるが、欧米の情報機関では歴史家が名分析官となった例が散見される。この分野で考察を行った元CIAの分析官は、歴史家というのは断片的な史料から、一連のストーリーを描き出すのに長けている、と言及しており、こういった人文系の学術的素養が時として情報分析のアートとして役に立つのかもしれない。
【第3回】に続く…



![[過去の放送]「僕らの地域活性化作戦」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130330.jpg)
![[過去の放送]「僕らの復興論」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130309.jpg)
![[過去の放送]「格差を超えて僕らの新たな働き方」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130101.gif)
![[過去の放送]「僕らの国際関係論」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20120929.jpg)