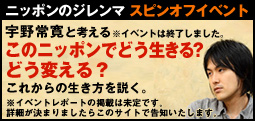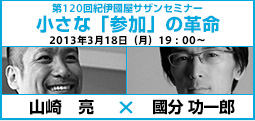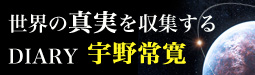「秘密保全法案」を考える――インテリジェンスに関するジレンマ【第4回】:小谷 賢
今年のはじめに起こったアルジェリアの人質事件は、日本政府の危機管理に対する様々な問題点を浮かび上がらせました。安倍政権のもとで日本版NSC(国家安全保障会議)の創設に対する気運が高まるなか、はたして国家や組織は情報をいかにして扱うべきなのでしょうか。インテリジェンスに関するホットな議論を、情報史の第一人者である小谷賢さんに解説していただきます。
小谷 賢 (コタニ・ケン)
1973年、京都府生まれ。防衛省防衛研究所戦史研究センター主任研究官。専門は、イギリス政治外交史、インテリジェンス研究。著書に『イギリスの情報外交 インテリジェンスとは何か』(PHP新書)、『インテリジェンス 国家・組織は情報をいかに扱うべきか』(ちくま学芸文庫)、『日本軍のインテリジェンス なぜ情報が活かされないのか』(講談社選書メチエ)など。
■秘密保全法案の論点
今年4月8日の東京新聞に「改憲準備の治安立法」、「戦争できる国の扉か」という過激な見出しが躍った。これは政府の秘密保全法案に対する反対表明だ。また昨年、民主党が秘密保全法案を検討したところ、日本弁護士連合会も反対を表明している。このように秘密保全法に対する反対は今でも根強い。しかしインテリジェンスを語るうえで、ここは避けて通れないテーマであるので、今回はこの問題について考えたい。
まず秘密保全法案とは、国の秘密が漏れないように、秘密に携わる国家公務員や政治家に守秘義務を設けることである。ここでポイントとなるのは、(1)国の秘密とは何か、(2)法律の適用範囲、(3)洩らした場合の罰則、といったあたりになろう。(1)の国の秘密に関しては、実は決まった定義がないといえる。そのため秘密が漏洩して表面化するたびに、それが秘密だったのか秘密でなかったのか、といった議論が繰り返されなければならなくなる。最近では2010年に海上保安庁からネットに流出した海保の巡視船と中国の漁船との衝突の動画が国の秘密にあたるかどうかで議論が行われた。このような議論を繰り返さないためには、まず国の秘密にあたるものを定義し、秘密にあたるものは指定してそれなりの扱いをしなければならない。さらに日本では情報漏洩事件となると裁判沙汰にもなる。日本の裁判は公開が原則であるから、たとえ軍事テクノロジーのような秘密であっても証拠として公の場にさらされる可能性も考えられる。
適用範囲については秘密を取り扱うことが想定される、公務員や閣僚級の政治家、また秘密に触れる可能性のある業者あたりになろう。秘密保護法とは国民の表現の自由を奪おうという類のものでは全くなく、国の秘密が漏れないようにするための制度なのである。
■秘密漏洩の罰則規定
次に洩らした場合の罰則である。現状では国家公務員の守秘義務違反というものがあるが、これは秘密を洩らした場合、1年以下の懲役、または50万円以内の罰金が課せられるというものである。これはこれで重い罰則のように思えるが、もし外国から働きかけを受け、「秘密を渡してくれたら謝礼に数千万円用意します」、と持ちかけられたとしよう。そうなると人によっては、「1年ぐらいの懲役なら……」ということでこれに応じるかもしれない。
これに対して諸外国では国家機密の漏洩は重罪と見なされている。常備軍を持たない中米のコスタリカですら、機密漏洩に対する懲役10年もの罰則規定が存在している。しかもコスタリカの場合は政治家や国の職員だけではなく、ジャーナリストや一般の国民も対象に規定しているため適用範囲はかなり広いといえるが、このコスタリカの事例は概ね欧米の基準に依拠している。さらに多くの国では罰則に加重主義を採用しているため、漏洩事案1件につき懲役10年、過去の事案が発覚して合計5件の秘密漏洩に手を染めていたとすれば、懲役50年だってありうる。これぐらいの厳罰になると、秘密を売り渡すことは割に合わないということになるので、秘密漏洩は起きにくくなる。
■秘密保全制度というインフラ
そもそも国が秘密を守らなければならないのは、国益や国民の安全のためである。例えば核兵器や生物兵器の設計図は国が秘密として厳格に取り扱わなければならない。もしそれが漏洩してテロリストの手にでも渡ろうものなら大変なことになるからだ。むしろ政府は国民を守るために、秘密保全の義務を有していると言ってもいいだろう。また秘密保全制度は情報を取り扱ううえでインフラの役割を果たしている。省庁間で情報を共有する際や、諸外国と情報交換する際、秘密保全というインフラが整っていないと、危なっかしくて情報交換などとてもできない。
国家の秘密は漏洩すればそれが国益を損ねるという意味で劇物にたとえてもいいだろう。通常、劇物を取り扱うには、法律で劇物を指定し、それを取り扱うための資格を設け、万が一事故が起こった場合の対応を決めておかなくてはならない。しかし我が国では、漏洩のリスクを考えると、秘密は役所の金庫にしまっておくのが最も安全という考え方も存在している。いくら日本の情報オフィサーが外国で苦労して情報を集め、それを緻密な分析にかけ、使うための情報(インテリジェンス)に昇華させたとしても、最終的に金庫に保管するのでは本末転倒である。情報とは使うためのものだからだ。そのため秘密保全というインフラを整備しないかぎり、情報機関や国家安全保障会議(NSC)を立ち上げたとしても、肝心の情報が回らない可能性も考えられる。この点は早急に改善しなければならないだろう。
■反対派の論点
ただし最初に書いたように、この分野は反対も根強い。反対派からの主な論点は、(1)国の秘密が際限なく拡大解釈される、(2)報道の自由への挑戦、(3)国民の知る権利への挑戦、あたりだろう。確かに国の秘密が際限なく拡大解釈されると、報道の自由や国民の知る権利などの根幹にかかわってくる問題となる。先ほど日本には国としての秘密がないと書いたが、実は日本にも厳格な罰則が課せられる秘密が二種類ある。一つは米軍から提供された軍事情報、そして防衛省・自衛隊の防衛秘密だ。前者は漏洩の場合、懲役10年以下、後者には5年以下の罰則が伴う。ただし軍事情報という分野において、何でもかんでも秘密に指定しているわけではない。秘密指定するためにはそれなりの手続きがあり、秘密指定後は秘密を逐一管理しなければならなくなる。そのコストを考えると、秘密の数は少ないに越したことはないといえる。
しかし、秘密の手続きが規定化されていない現場では逆のことが生じる。とにかく漏れると困るので、何にでも「秘」のハンコを押したほうが安全という考え方である。しかしそれだと本来は国民に開示してもよさそうな情報ですら、秘密扱いになってしまう。ルールが明確化されていないと、役所の解釈や裁量の余地が拡大してしまうということだ。すなわち秘密保全法と秘密指定の規定があれば、秘密の数は自然と制限されていくことになるだろう。
■秘密保全法は何のためにあるべきか
また機微な情報が文書の形で残されないこともあると聞く。それは常に漏れる危険性を秘めているからだ。そのため重要な秘密は紙ではなく、口頭によって一子相伝的に受け継がれていく。しかしこのようなやり方は極めて分かりにくいうえ、国民にとっても不幸なことである。機微な内容であっても文書化して秘密として保管しておき、何十年か経った後に歴史資料として公開すれば、国民の知る権利も保障されるのではないだろうか。
国民の知る権利や報道の自由については憲法第21条で保障されているという説もあるが、それを持ち出さなくても前者については2001年から施行されている情報公開法があり、後者については1969年の博多駅事件判決や1978年の西山事件判決などで、取材の自由が認められている。「秘密保全法が制定されると自由な取材ができなくなる」という声も聞かれるが、日本よりもはるかに厳格な法律を持つ欧米でも実際にジャーナリズムはきちんと機能している。特にアメリカでは過去、報道機関によって何度も国を揺るがすようなスクープがすっぱ抜かれたため、今でも政府機関との間にいい意味での緊張感が保たれているという。
このように秘密保全法を制定することで、直ちに国民に不利益が生じるとは考えにくい。むしろそれは国益のためであり、ひいては国民の安全のためだと言えるのである。
【第5回】に続く…



![[過去の放送]「僕らの地域活性化作戦」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130330.jpg)
![[過去の放送]「僕らの復興論」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130309.jpg)
![[過去の放送]「格差を超えて僕らの新たな働き方」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130101.gif)
![[過去の放送]「僕らの国際関係論」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20120929.jpg)