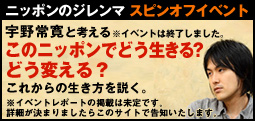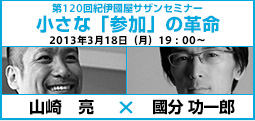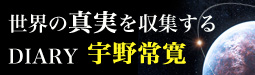人文学不振の理由とは? ―宗教学から見る今日の社会 大田俊寛 第1回(全6回)
宗教への問いは、現代社会に必要なのか――? 2011年に『オウム真理教の精神史』(春秋社)を出版し、宗教研究の再生に挑んだ気鋭の宗教学者・大田俊寛。理論的な考察に徹することでみえてくる、現代社会の宗教の姿とは。宗教学の今日における意義と可能性を熟考する。
大田 俊寛 (オオタ・トシヒロ)
1974年生まれ、宗教学者。埼玉大学非常勤講師。著書に『オウム真理教の精神史』『グノーシス主義の思想』(ともに春秋社)など。
Q,宗教学の研究者として、現代の宗教学の役割とは、ひいては、人文系の学問の役割とはどんなことだと思われますか。
A,宗教学の役割とは、「そもそも宗教とは何か」という問いに答えること、そして、歴史的に存在してきた宗教、世界中に存在する宗教に対し、それがどのような経緯とメカニズムによって成立しているのかを、可能な限り客観的に分析することです。
宗教学のこれまでの歴史においては、こうした役割を果たすための学問的業績が蓄積されてきたことは確かですが、思うようにはいかなかったというのも、また事実でしょう。現在の日本の宗教学や、その他の人文学について言えば、そこには大きく二つの問題があるように思われます。
一つ目は、戦後の人文系の諸学において、戦前・戦中の国家主義への反動から、「左翼的イデオロギー」が必要以上に幅を利かせたことです。まず、五〇年代から六〇年代にかけては、マルクス主義的な革命運動や反国家主義が、アカデミズムにおいても強い勢いを保っていました。一つの大学のなかに、何人ものマルクス主義の学者が在籍しているというような状況があったわけです。そして七〇年代以降、安保闘争の終焉や学生運動の退潮によってマルクス主義の勢いは衰えていきましたが、同種の反体制的なエートスは、屈折した形でポストモダニズムやニューエイジ思想に継承されました。こうした諸思想においては、革命論が次第に現実的なものから幻想的なものへと変化していき、個人の意識が変われば世界が変わるといった「精神革命」や、国家や共同体の頸木から軽やかに逃走すべきとする「スキゾ革命」が主唱されるようになりました。
八〇年代の多くの知識人や文化人がオウム真理教を肯定的に捉えたのは、こうした背景が存在したからです。もちろん、近代の政治体制や資本主義的な経済システムに対して批判的な考察を行うのは、とても大切なことです。しかし、現在のわれわれの生活がそういった制度やシステムに支えられているという現実から目を背け、それらはすべて「悪」である、それらを超克することが「善」である、ゆえに理論より実践が重要だ、と言い出してしまえば、「事柄そのものを価値中立的かつ客観的に分析する」という近代学の理念は見失われ、研究者はもはや、ただの「イデオロギー的な扇動家」になってしまいます。九〇年代以降、ポストモダニズムやニューエイジ思想もまた魅力を失って退潮していきましたが、いまだにその負債を十分に清算できていないというのが実情でしょう。
二つ目に、その対極の問題として、研究者の官僚化、あるいは「サラリーマン化」という問題があります。マックス・ウェーバーがすでに指摘していたように、近代社会においては、さまざまな組織が次第に専門分化・官僚化するという傾向が見られますが(ウェーバーは『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の末尾で、これを端的に「鉄の檻」と名指しました)、そういった状況を大学も免れていません。現在の学問の基本を忠実に守って「真面目な」論文を書こうとすれば、良くも悪くも高度に専門的なものとなり、国内ではその論文の内容を理解できる人が数人しかいない、世界全体で考えても一〇〇人はいない、という状態になるのは、きわめてよくあることです。そして、日本の大学の図書館には、誰にも読まれた形跡のない学術雑誌論文や紀要論文、科研費報告書(=国から助成を受けた研究についての成果報告書)が、膨大に所蔵(死蔵?)されています。
もちろんそこには、良質な論文や報告書が数多く含まれていますが、しかし他方、あえて批判的に言えば、サラリーマンが業務のために無機質な書類を書くように、研究者が無味乾燥な論文を量産するということが常態化してもいるのです。コミュニケーションがごく少数の研究者のあいだだけで閉じてしまっており、その成果をどうやって一般社会に伝えていくのかということに、十分な配慮が払われていない。これが理系の研究であれば、「専門家だけが分かっていればいい」ということが多々あります。テレビやコンピューターなど、一般人が内部の仕組みを分かっていなくとも、その器具の恩恵にあずかれるといったことは、沢山ありますから。しかし、文系の学問においては、そのようなケースは、ほとんどありません。学問によって生み出された知識や認識が何らかの形で社会で共有されなければ、事実上、何の意味もないものが大半です。誰も読まない論文や報告書をどれだけ図書館に積み上げても、何も起こらないし何も変わらない。文系の研究者は、こうした状況をどうにかしなければならないという問題意識を切実に持つ必要があります。
現在の人文学が全体として低調なのは、幻想的にしか思考することができないポストモダン系の扇動家か、何を研究しているのかすら、よく分からない狭隘な専門家のどちらかしか見当たらないからだと思います。見識のある人であれば、こういう連中は相手にするだけ時間の無駄と考えて当然です。また、再びオウムを例に取れば、こうした状況のなかで、教団や教義の性質をよく見極めないまま、一部の研究者がオウムを礼賛・擁護するという現象が生まれました。そして、九五年にサリン事件が起こった後には、「オウムとは結局何だったのか」という問いに答えてほしいという社会からの要請が明確に存在したにもかかわらず、それに正面から答えようという研究者は、日本には現れませんでした。人文学のこうした状況を変えるのはきわめて難しいでしょうが、軽率に実践に踏み出さず理論的な考察に徹すること、自分が専攻する学問に差し向けられた基本的な問いをおろそかにせず、それについての答えを社会に伝えるという本来の職分を忘れないことが、とても大切だと思います。
第2回 なぜ宗教学を志したのか に続く



![[過去の放送]「僕らの地域活性化作戦」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130330.jpg)
![[過去の放送]「僕らの復興論」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130309.jpg)
![[過去の放送]「格差を超えて僕らの新たな働き方」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130101.gif)
![[過去の放送]「僕らの国際関係論」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20120929.jpg)