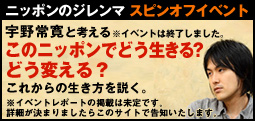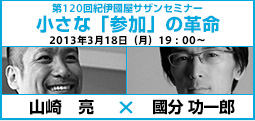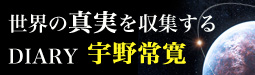「“救国”の大学論2014」番組収録後インタビュー:横田幸信
2014年4月27日(日)0:00~01:00[26日(土)深夜]放送予定のニッポンのジレンマ「救国の大学論2014」収録後、横田幸信さんにインタビューを行いました。
横田 幸信 (ヨコタ・ユキノブ)
1980年生まれ。東京大学i.school ディレクター。イノベーション・コンサルティング会社i.lab, CEO。小学生向けの教育系NPO法人 Motivation Maker ディレクター(代表理事)。九州大学大学院理学府修士課程修了後、野村総合研究所にて経営コンサルティング業務に従事し、東京大学大学院工学系研究科博士課程中退を経て現職。現在は、大学と産業界の二つのフィールドにて、イノベーションの実践活動と科学・工学的観点からの研究・教育活動を行っている。
――今回の番組で“最も伝えたかったこと”は何でしょうか。
横田 私が今さら言及するまでもなく、大学全入時代やオンライン教育の勃興、グローバル化、ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)の進化を視野に捉えると、私たちは「大学」という存在の本質を問われる時代に生きています。そうした社会環境が大きく劇的に変化している中で、これからの大学について議論する際には、これまでの社会通念や前例などの本質的ではない表面的な制約条件が、その議論の前提として必ずあるように思います。
例えば、高校卒業して18歳で大学に入学するということ、大学・大学院を卒業して企業に就職するということ、大学は研究を通じた教育を行うということ、企業が求める人材像を考慮したいということ、大学のポストが増えず新しい教員を雇用できないということなど、表面的制約条件は挙げていくときりがありません。
しかしながら、思い返してみると、そもそも大学の本質は、制約に縛られるというより、むしろ「自由」で、外部の要請にただ応えるというよりは、むしろ「主体的」で、時代の変化に沿うというより、むしろ時代の「革新」を進める人材を育成するところにあったのではないでしょうか。これからの日本を創るそうした人材を育てられる大学を取り戻すためには、前例や社会通念に捕われず、「自由で主体性を持った知的格闘」とすら言える議論、そして何より実際の具体的行動が必要だと思います。
「総論賛成、各論反対、そして自分は行動しない」ではなく、逃げ場のないこの状況を打破する、主体性のある行動を少なくとも私はとり続けたいと思っています。
――今回の番組で“興味を持った、あるいは、印象に残った発言や話題”はありましたか。
横田 今回の登壇者の方々の大学生時代のエピソードの中には、「ゼミや研究、合宿などでの学生と先生との全人格的なコミュニケーションを通じた成長体験」が多くあったように思います。私自身の大学生活を思い返してみても、そのようなエピソードは多いです。大学が提供する高等教育の分野においてもオンライン教育の機会が増えているわけですが、実地で学ぶ狭義の「大学」の存在意義というのは、そうした人と人の直接的なコミュニケーションを通じた全人格的な教育と成長にあるのかもしれません。
学生も先生も建設的で知的格闘が常に行われている緊張感のある雰囲気を大事にしながら、大学生活を送れるとよいですよね。損得抜きで、自然や社会の本質について全身全霊で学び議論することを通じて全人格的に育ってほしいですし、私もまだまだ成長していきたいと思いながら大学で仕事していきます。
――日本の大学が生き残るためにできることは?
横田 日本のトップ10水準の大学では、少なくとも大学院修士課程以上において、英語での講義・論文執筆を通じて学位が取れる状況を整備する必要があると思います。そうすることで海外からの留学生を一定数確保できるはずです。 また、そうするためにも、日本の大学の講義や教育プログラムを世界の人に知ってもらう機会として、英語での講義のオンライン配信や夏期休業中のサマープログラムの充実などが望まれます。 特に新興国で将来知的職業に就くことが期待される若者の多くに日本の文化や習慣、ライフスタイルを知っておいてもらうことは、学問的な側面だけではなく、経済面や政治面から見ても多いに意味のあることだと思います。
――今の大学生にアドバイスはありますか?
横田 大学生は、経済的な面では親御さんに頼っている部分は残るとしても、その他の部分では充分に一人前の大人だと思います。皆さんが現在大学にて勉学に励んでいるのは、社会人になる準備期間としての未熟な存在ではなく、社会の中で勉学に励む役割を持っている一人の人間だとも言えます。その点で、しっかり責任感と自負心をもって生活しておくとよいでしょう。 また、今この瞬間に自らの知的探究心と数々の挑戦を受け入れてくれる場所・期間としての大学や学生生活を、自らの社会の中での役割として認識すると同時に、個人としても存分に楽しんでください。


![[過去の放送]「僕らの地域活性化作戦」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130330.jpg)
![[過去の放送]「僕らの復興論」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130309.jpg)
![[過去の放送]「格差を超えて僕らの新たな働き方」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130101.gif)
![[過去の放送]「僕らの国際関係論」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20120929.jpg)