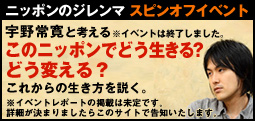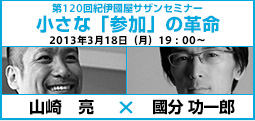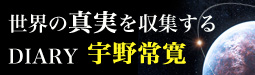「僕らの新グローカル宣言」番組収録後インタビュー:山口純哉
2013年12月22日(日)0:00~1:15〔土曜深夜〕放送予定のニッポンのジレンマ「僕らの新グローカル宣言」収録後、山口純哉さんにインタビューを行いました。
山口 純哉 (ヤマグチ・ジュンヤ)
1971年、愛媛県生まれ。長崎大学経済学部准教授。専門は地域経済。グローバルな社会、しかも人口減少・少子高齢化が進む地方で、豊かな暮らしを持続するためには何が必要か? 地域外からお金を獲得できる産業、地域内でお金を循環させることのできるソーシャルビジネスの創出など、地域のグランドデザインづくりを目指す。
――今回の番組で“もっとも伝えたかったこと”は何でしょうか。
山口 「グローバル化」が声高に叫ばれ、地方の経済社会の存続を危ぶむ声も聞こえてきますが、悲観する必要はなく、まだまだ地方には可能性があるということです。
経済活動にしろ文化活動にしろ、これまでの地方は“あるもの”を“あるがまま”に使ってきました。たとえば観光に関しては、歴史的な観光資源を訪れてもらうための交通体系を整備したり、情報発信に尽力したりと、資源磨きではなく、資源に触れてもらうための手段の整備に尽力してきたような気がします。しかし、交通や情報発信など手段の地域間格差がなくなりつつある今、地域の存続は、その地域が有するヒト、モノ、情報の魅力にかかってきています。また、その資源が魅力的であるとの思い込みも多々あったのではないかと思います。
地方に魅力的な資源があるのかと悲観的な見方をする方もいらっしゃいますが、ヒト、モノ、情報など、発掘されていない、磨き足りない、創れる資源はあると思っています。そして、各地域の魅力的な資源が輝きあう世の中こそ、グローカルな時代のあるべき姿だと考えています。一気に大きな成果をあげることはできないかもしれませんが、技術にしろ文化にしろ、小さな資源が残っている、創られ続けるかぎり、地方に可能性があることだけは、ぜひ伝えたいと思っていました。
――番組内で“興味を持った発言”や“印象に残った発言や話題”はありましたか。
山口 伊藤直樹さんの「アダプテーション」という言葉が印象的でした。企業のCMをグローバルに展開するためには、単純に言語を翻訳するだけでは不十分で、各国の文化や社会状況を踏まえていないと伝わらないそうです。だからこそアダプテーション(適応)が必要なんだというお話でした。
じつは、それこそが地方が直面している課題です。地方に住んで地元を愛している方が、「これが良いんだ」「ここが素晴らしいんだ」と自分本位にPRしたところで、東京や海外の人には伝わりません。たとえば、私のゼミに所属する留学生の一人は、長崎市内に点在する史跡の説明書きを見ても、歴史的な予備知識が日本人とは異なるので、言葉はわかっても意味はわからないそうです。資源があるだけでは不十分で、国内外問わず、発信する相手の立場に立って資源を磨く、伝えることが「グローカル化」を図るうえでの課題です。そういう意味で、伊藤さんのご発言は、今回の議論を象徴するものだったように思います。
――ご自身の研究・関心領域のなかで、もっとも如実に“東京”と“地方”の格差が生じていると思うのはどんなことでしょうか。また、その格差をどうするべきだと考えますか。
山口 東京は、すでに総力戦をたたかっていると思います。ヒト・モノ・カネ・情報のあらゆる資源が総動員され、経済活動や文化活動が展開されています。ところが地方に行くと、まだまだ眠っているものが多い。そこが「東京」と「地方」の差だと思いますし、地方はその差を活用すべきだと考えています。
近ごろ、地方の産業がモノやサービスをアジア市場へ売り込もうという動きが活発ですが、日本から上海へ鮮魚を輸出する代表的な企業は長崎にあります。
また、観光に目を向ければ、市民と行政とが協働して地域資源を発掘・発信している例として、2006年から取り組まれている「長崎さるく(「さるく」とは、まちをぶらぶら歩くという長崎弁)」があります。それまで、観光都市としての長崎が観光客に提供してきたのは、グラバー園や原爆資料館など多くの人が知っている、いわば定番メニューだけでした。しかし、その裏には、市民しか知らない様々なストーリーがあって、それを市民主体で掘り起こして見える化(=マップ化)し、それを片手にぶらぶらするもよし、ボランティアガイドと一緒にぶらぶらするもよし、マニアックな知識を得るための講座とセットでぶらぶらするもよしという多様なまち歩きメニューを国内外の方々に提供して、観光都市としての息を吹き返しつつあります。
このように、昔のようにリトル東京を目指すのではなく、地域特有の資源を掘り起こして発信することこそ、まさにグローカル化の第一歩だと思っています。
――この番組では、70年代以降生まれを「ジレンマ世代」と位置づけています。この世代が東京を生きる/地方を生きるうえで、上の世代ともっとも異なってくるのはどんなことでしょうか。
山口 明確に世代を区切ることは難しいと思いますが、もはや全員が同じ方向を向いた社会ではない、ということだけは明らかではないでしょうか。
昔は「人手が足りない」=「地方から東京へ」というストーリーがあって、個人はその流れに乗っかることで、社会に参画していました。ところが現在は、量的な問題ではなく質的な問題として、いかに社会に貢献できるかという視点から、個人の存在意義が問われるようになってきている。そのあたりが決定的な違いだと思います。
すこし前まで共有されていた「右肩上がりの社会」という前提も、人口減少や少子高齢社会などに直面する成熟した時代にあって、すでに終わりを迎えていると思います。そんな社会を生きていく世代は、自分の生活を見つめ直し「足るを知る」ことに向き合う必要があるのかもしれません。かつて、シューマッハーという経済学者が『スモール イズ ビューティフル』という本の中で、身の丈に合った技術、生活や社会が人間にとって心地良いという主張を展開していました。シューマッハーの主張に完全に同意するわけではありませんが、これからは縮んでいくことを前提に社会を設計する必要があると思います。
もちろん、グローバル競争の荒波に挑戦して、打ち勝っていこうとする人たちを否定するわけではありません。それはそれで大事です。しかし、現在の地方にとってより重要なのは、少子高齢化や人口減少などの課題を解決する「ソーシャルビジネス」のような取り組みの成功例を積み上げていくことだと思います。大儲けはできませんが、社会問題の解決と必要最小限の利益を両立させるようなビジネスです。幸いにして、地域の存続に危機感を持っている地方の学生の間では、こうしたビジネスへの関心も高まっています。ややファッションめいた「甘さ」を感じないこともありませんが、70年代以降生まれの生き方、ひいては地方の生きる道として歓迎すべき傾向だと思います。
ローカル、グローバルのいずれに軸足を置くにせよ、多様な生き方が許される時代であることには間違いないと思いますので、自分がいかなる生き方を目指すのか、その中で社会にいかに貢献するのかを見極めて、グローカルな時代の中で輝いていって欲しいですね。


![[過去の放送]「僕らの地域活性化作戦」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130330.jpg)
![[過去の放送]「僕らの復興論」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130309.jpg)
![[過去の放送]「格差を超えて僕らの新たな働き方」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130101.gif)
![[過去の放送]「僕らの国際関係論」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20120929.jpg)