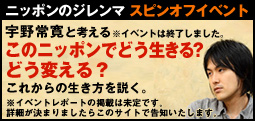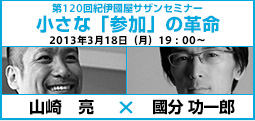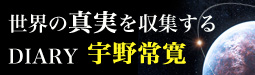一冊の本を全力でつくっているうちは、まだ編集者じゃない:柿内芳文
163万部を売り上げた『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』をはじめ、『99.9%は仮説』『若者はなぜ3年で辞めるのか?』など、光文社新書でヒット作の編集を担当してきた柿内芳文さん。2011年9月からは、講談社初の社内ベンチャーとしてできた新しい出版社・星海社で、「星海社新書」の編集長を務めています。競争が激しい出版業界でヒット作を生み出し続ける哲学とは何か。NHKで働く若手が集まる「ジセダイ勉強会」からのレポートです。

柿内 芳文 (カキウチ・ヨシフミ)
1978年生まれ。星海社新書編集長。光文社を経て2011年9月より現職。163万部を売り上げた『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』ほか『99.9%は仮説』『若者はなぜ3年で辞めるのか?』『武器としての決断思考』など、新書のベストセラーの数多く手がける。
神原 一光 (カンバラ・イッコウ)
1980年生まれ。NHK放送総局 大型企画開発センター ディレクター。主な担当番組に「NHKスペシャル」「週刊ニュース深読み」「しあわせニュース」「おやすみ日本 眠いいね!」。著書に『ピアニスト辻井伸行 奇跡の音色 ~恩師・川上昌裕との12年間の物語~』(アスコム)、最新刊は『会社にいやがれ!』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。
神原 本日の勉強会は、163万部を売り上げた『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』を光文社に入社して3年目でつくったほか、『99.9%は仮説』『若者はなぜ3年で辞めるのか?』『就活のバカヤロー』『4−2−3−1』『ウェブはバカと暇人のもの』『非属の才能』など新書のベストセラーの数多く手がけて2010年9月に星海社という新しい出版社に電撃移籍、さらには、NHKEテレNHK総合「NEWS WEB 24」のネットナビゲーターでお馴染みの瀧本哲史さんの『武器としての決断思考』『武器としての交渉思考』。また「ニッポンのジレンマ」に初登場した木村草太さんの『キヨミズ准教授の法学入門』、木暮太一さんの『僕たちはいつまでこんな働き方を続けるのか?』など、今、まさに勢いのある新書をバンバンつくっていらっしゃる星海社新書編集長の柿内芳文さんです。本日は柿内さんが「どういう想いで新書をつくっているか」などを伺い、テレビの番組づくりに通じることを学びたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
柿内 柿内です。ご紹介ありがとうございます。こちらこそ、よろしくお願いします。あと、神原くんと僕は昔からの友人なので、恥ずかしいから「くん」付けでお願いしますね。
神原 わかりました。じつはこの「ジセダイ勉強会」の「ジセダイ」は、星海社新書のウェブサイト「ジセダイ」から影響を受けて名づけさせて頂きました。漢字だとお堅いけど、片仮名ですと、なぜか疾走感のある印象になりますね。
柿内 そうですね、一緒に「ジセダイ」を盛り上げていきましょう!
 柿内芳文さん。
柿内芳文さん。
新書は「知の〝入り口の入り口〟を、若い人に提供するメディア」
神原 柿内くんといえば、光文社であれだけの大ヒットを連発しながら、星海社という新しい出版社に電撃移籍したことが、話題になりましたよね。
柿内 僕は2002年に新卒で光文社に入り、創刊してまだ半年しか経っていなかった光文社新書の編集部に配属されました。そこで、さきほどご紹介いただいたような山田真哉さんの『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』や城繁幸さんの『若者はなぜ3年で辞めるのか?』などの新書を9年ぐらいつくってきました。そして、2010年に講談社初の社内ベンチャーである星海社が創立するときに声をかけていただき、社員ではなくフリーランス契約ということでいろいろと悩みもしましたが、「面白そうだ!」「ここでチャレンジしなければ男じゃない!」ということで、結局光文社を辞めてフリーになりました。星海社では、星海社新書という新しい新書レーベルを立ち上げて、2012年の9月で1周年になりました。
神原 もう27冊も出しているんですね。新しく立ち上げたレーベルにしては、かなり多いように思えるのですが。
柿内 そうですね。たしかにたくさんつくることは大変なのですが、星海社新書の影響力をもっともっと強めていきたいので、コンスタントに月3、4冊は出せるようにしていきたいと思っています。光文社では入社以来ずっと新書をやってきたので、「新書以外の新しいことを始めよう」と思って星海社へ移ったのですが、じゃあ何をやろうかと考えたとき、「改めて新書をやろう!」という結論に戻ってきました。「新書ってそもそもなんだっけ?」と、自分のやってきた過去の仕事を初めて振り返ってみたんですね。本質を突き詰めると、新書というのは「知の〝入り口の入り口〟を、若い人に提供するメディア」である――1ヶ月ほど考えて、その定義付けにたどりつきました。
神原 「入り口の入り口」ですか?
柿内 そうです。もともと新書というのは1938年創刊の岩波新書が始まりですが、その当時は大学などの「アカデミズムの世界」が現在よりもはっきりとあった時代で、一般的な読者との間に距離がありました。専門書は知識人のもので、大衆と学問の世界との間に、大きな川が流れていたんですね。その両者をつなぐものとして「新書」がありました。僕はそう捉えています。新書が、専門的な学問ジャンルや知識への「橋渡し」の役割を担っていたわけです。
神原 新書は「川に架かる橋」のイメージだと。
柿内 その通りです。そして、廉価でハンディ・コンパクトな新書は、若い人が新しい知識を身につけるのにも、もってこいでした。牛丼屋のコピーじゃないですが、「安い・軽い・読みやすい」は大きなメリットですよ。かつての大学生は、岩波新書や中公新書、講談社現代新書を読んで、学問の世界に入っていったんですね。まさに「知の入り口」です。でも、いまでは新書はそうは捉えられていません。「新書ブーム」という言葉が象徴するように、「新書にすれば売れそうだ」「すぐ本にできそうだ」ということで、無目的に惰性で新書をやっているところも多いと思います。また、新書を単行本よりも一段下のものとして捉えている人も多い。特に編集者や作家に!
神原 おっ、柿内くん、ちょっと憤っていますね。
柿内 いや、そうではなくて。ただ、残念なだけなんです。新書はそんなものじゃない、と叫びたいだけです(笑) 僕は「新書ブーム」ではなく「教養ブーム」を起こしたいんですね。それも、自分よりも年下の若い世代のあいだに。だから、大きな目的をもって、意識的に、積極的に、新書レーベルをつくることを決意したんです。そして、次世代の・次世代による・次世代のための「武器としての教養」というコンセプトと共に星海社新書を創刊し、同時にウェブサイト「ジセダイ」も立ち上げました。新書は、老人向けに「老い」や「健康法」「年金」の話をするメディアでは決してない。これからの日本を担う世代の人間たちが、悩み、考え、行動するのを手助けするものでなければいけないんです!
神原 いやー、熱いですね。
柿内 若い人から「熱」を取ったら、何が残りますか? 寺山修司さんは、「経験の重みを原点にすると老人だけが世界について語る資格を持つ。ぼくらは地球のふちに腰欠けて順番を待つしかない」と言っていますが、本当にその通りです。閉塞感を理由にして行動しないのではなく、閉塞感を打破するために行動していく。だってそのほうが断然楽しそうじゃないですか。僕は、多少の使命感もありますが、なにより人生で楽しいことをやっていきたい。こんなに楽しい時代はないし、歳を取れば取るほど楽しくなっていくので、来年になるのが楽しみでなりません。
神原 そうそう、柿内くんはいつも楽しそうだからなー。
柿内 いや、神原くんだってそうじゃない!あと、いつも青臭い話しかお互いしないし。
神原 たしかに(笑)。で、話を戻すと、新書というのは「知の〝入り口の入り口〟を、若い人に提供するメディア」だということですが、「入り口」と「入り口の入り口」はどう違うのでしょうか?
柿内 「入り口の入り口」というのは言葉のあやで、要は「わかりやすい入門書」ということです。入門書をうたう本は多いですが、本当に入門書足りうるためには「2つの自分」に橋を架けてあげなければならないんですね。星海社新書では、新書というメディアの特性を最大限活用するために、「わかりやすさ」に徹底的にこだわっています。
神原 「2つの自分」ですか?
柿内 そうです。一つ目の自分は、「自分ごとにする」ということです。どんなに面白いことや、知っておくべき知識や思考法があったとしても、対岸の火事のような存在であったら、知りたいとは思わないし、ましてや本なんて読みません。たとえば、「会計学」は対岸にあるような話ですが、これが「さおだけ屋はなぜ潰れないのか?」となると、一気に「自分ごと化」してきますよね。対岸から此岸に橋を架けるんです。
神原 なるほど、たしかにそれはわかりやすいし、「会計学」という存在が身近に感じられますね。
柿内 もう一つの自分は、「自分でもわかる」です。いくら自分ごととして捉えることができるようになったとしても、表現がまどろっこしかったり、専門用語を知らないと理解できないような内容であれば、そこで読むのをとめてしまうでしょう。だから、僕が読んでもわかる、ということが重要になってきます。ここで言う「自分」というのは僕のことで、その僕はバカな存在なんですね。けっして賢くはない。
神原 え? 編集者である柿内くんが「バカ」ということ?
柿内 そうです。僕は編集者としての自分のことを「プロの素人」だと定義しています。たとえば会計の企画を進めていくと、どんどんそのジャンルに詳しくなって、プチ専門家になってしまったりするのですが、そうすると「自分でもわかる」の基準があやふやになってしまいます。徐々に一般読者よりも著者の考えに近づいていくので、たとえば「財務諸表ってなんですか?」とか「簿記ってルビをつけないと『ぼき』って読めないですよ」といったバカな質問もできなくなる。編集者が専門的になればなるほど、読者が立っている岸からの景色が見えなくなりやすいのだと思います。
神原 なるほど。目線や立ち位置、読み手の気持ちを編集者として考えるということですね。
柿内 そう。そこで僕がやっているのは、たとえば、いちばん最初に原稿を読んだときの感想を、本当にバカな質問も含めて、すべて徹底的に書き残す、ということです。そうやって「バカな素人の自分」という基準を消さない努力をしています。二度目に読むときは、もうファーストインプレッションは消えてなくなっているんですね。じつはその昔、ちょっと意味がわかりづらいなー、と最初に読んだときに違和感を感じた箇所を最後までそのままにして出版したら、読者からの手紙でまったく同じ「ここがよくわからなかった」という感想が届いたんですね。やっぱり「僕がわからないことは読者もわからない」というのを絶対的なスタンスにしないといけないと、猛省しました。二度目に読んだときは、もうなんか「わかったつもり」になっちゃうんですよ。
神原 これは、番組を作る時にも重なりますね。勉強になります。
柿内 ともかく、「2つの自分」にさえ橋を架けることができれば、それは入門書足りえます。そこまでしてはじめてお金を取れる。「○○の話をするとむずかしくなる」といったように、話題やテーマそのものに難易度があるわけではなく、橋渡しができていないから難しく感じるんですね。橋さえ架ければ、財務諸表もPLもBSも管理会計も、超わかりやすく、そして面白くなりますよ。かのゲーテは「教科書は、魅力的であってもらいたい。魅力的になるのは、知識と学問のもっとも明朗で近づきやすい面を出して見せるときに限るのだ」と言っていますが、まったく同じスタンスです。「もっとも明朗で近づきやすい面を出して見せる」というのが、「2つの自分」のことであって、僕は「魅力的な教科書」をつくりたいんですよ!
タイトル付けで大切なのは、「対話が生まれるかどうか」
神原 星海社新書のタイトルは、『仕事をしたつもり』や『じじいリテラシー』、『武器としての決断思考』や『僕たちはいつまでこんな働き方を続けるのか?』など、明らかに他社の新書とは言葉のチョイスが違いますよね。そういうアイデアのタネや素材はどこから拾ってくるのでしょうか?
柿内 そうですねー、「タイトルの付け方がうまい」と評価をいただくことも多いのですが、タイトルやキャッチコピーは、じつは優先順位としてはいちばん最後なんですね。「2つの自分」や「新書はこうあるべき」といった自分なりのベースの考え方があって、そこから派生していくものが、タイトルやコピーです。いちばん重要なのは、「企画」であり、「内容」そのものですよ。だから、仮に他人にタイトル付けのテクニックを教えたとしても、あまり意味がないというか、再現性がないですね。テクニックでどうにかなるものではありません。根と幹があって、はじめて枝が生えてくるのに、枝の話だけしても意味はありません。まずは本質やコアの部分を考えることが重要だと思います。僕のつけるタイトルはインパクト狙いだと思われることも多いのですが、最初から狙ってつけているのではなく、根や幹の部分から考えていったら、結果としてインパクトが出た、ということが多いですね。この順番を間違えると、大変なことになりますよ。
神原 でも、何かテクニックがあるんじゃないですか? ぜひ、1つでいいので教えてくれませんか?
柿内 うーん、テクニックではないですが、僕がタイトル付けで気をつけているのは、「対話が生まれるかどうか」ですね。書店で本を見かけた人との間に対話が生まれないと、手に取ってはもらえないと思っています。そこは、徹底的に商売人の立場に立ちますね。読者は「消費者」であり、タイトルは「宣伝コピー」です。プロの素人として、メーカーに勤めている自分が見たらどう思うか、10年前の自分は何を感じるか、などと考えていき、最後の最後は「この本は〝誰に何を〟伝えたいか」という想い・熱の部分を大事にして、最終判断を下しますね。幹から枝葉のことを考えていき、最後はやっぱり幹に戻っていくイメージでしょうか。
神原 なるほど。私も、番組をつくっているときに、「ところでこの番組って誰得なの?」ということがつねに頭の中にあります。身近な感じがしますね。
柿内 「誰得」って「誰に何を」という言葉とほぼ同義かもしれませんね。僕がいつも想起しているのは、休日の渋谷駅前のスクランブル交差点ですよ。あの群衆に遠くから石を投げれば、ぜったい誰かに当たりそうな気がしますが、そういった力や意志のない投石は、案外誰にも当たらず、ぽとりと地面に落ちてしまうものです。そういった本が多すぎませんか? 英語の本が当たったら英語の本、老いの本が当たったら老いの本、商売といえばそれまでですが、「誰に何を」という目的も熱も矜持もない本が、毎年どんどん増えているような気がします。よく出版不況と言いますが、僕らがそれを生み出しているんだと思いますよ。他人事みたいに言っている人が多いけれど。とにかく、例えが適切かどうかわかりませんが、群衆からひとりを引っ張り出し、その人の胸ぐらをつかんで、全力で顔面にぶつけるくらいのことをしないと、とても石は当たりません!
神原 うーん、またしても熱い!
これからは「コンセプトの時代」がおとずれる
神原 ここからは、会場からの質問をもとに、さらに話を深めていきましょう。
Q:フレッシュで尖っている「面白いアイデア」は、20代・30代なら誰しもが持っていると思うのですが、年上のおじさん(上司)のフィルターを10人も通すと、平均的で凡庸なものに「洗練」されてしまうことがあります。入社3年目で『さおだけ屋〜』という大ヒットを飛ばした柿内さんは、おじさんたちをどう説得してきたのでしょうか?(ジセダイ勉強会参加者)
柿内 あー、まさに『じじいリテラシー』ですね(笑)。
神原 私も『じじいリテラシー』読みました。これ絶対に使える本だと思うので、オススメですよ。
柿内 昔からよく言われていることだと思いますが、まずこまめに顔を見せるとか、話をしっかり聞くとか、挨拶をきちんとするとか、食堂で隣に座って話しかけて仲良くなるとか、けっこう基本的なことが大事かもしれませんね。出版社でいえば、私は書店を担当している営業の部署によく顔を出す編集者だったと思います。つくるだけに集中して「あとは良い本だから売れる」という人もいるのですが、結局、部数を決めたり、何を重点的に仕掛けていくかを決めていくのは販売部でしたので、コミュニケーションを取っていくしかないなと思っていました。
神原 企画を通すのはやはり編集長ですか?
柿内 そうですね。いくら企画が通らなくても、「俺のこの企画すげえ。このアイデアをわからない老害どもめ!」なんて態度じゃ、孤立していくだけです。ただ、全部にイエスマンだと可愛げはない。たまに反発するくらいが、ちょうどいいんですよ。イメージとしては、犬に腕をかませてあげるような感じでしょうか。その犬になれ、と。主導権は買い主である上司が握っているところが肝です。
神原 なるほど、それはわかりやすい例えですね。
柿内 あと、「コイツ何か青臭いなぁ」という全力さと若さは、20代・30代にとって、ものすごい武器になると思うんですよね。今日もけっこう青臭い話をしていると思うんですが、ふだんから普通にやっているので、これはもう素ですね。特に恥ずかしさはありません。でもじつは、最初は計算から入ったところもあります。あまりに企画が通らなかったので、本当に切羽詰まっていたんですね。でもそうやって、ある意味「演技」をしていると、いつの間にかそれが素になってしまうので、けっこうおすすめの方法ですよ。
神原 なるほど、最初はデキる上司や先輩のやり方を「真似る」のも手ですよね。
柿内 そうですね、著者の千田琢哉さんも、『デキるふりからはじめなさい』のなかで、それを「生態模写」と呼んで推奨しています!
神原 じゃあ、つぎの質問にいきましょう。
Q:柿内さんは31歳にしてレーベルの編集長になられたわけですが、肩書きがついて、何がいちばん変わりましたか?(ジセダイ勉強会参加者)
柿内 そうですね。いちばん変わったのは、より中長期の視点に立てるようになったことだと思います。新書というのは「10年単位」で売っていく、ロングスパンの商売なんですね。だから、もともと流行に左右されない普遍的な問題をテーマにしてきたところがあるんですが、編集長になる前は「一冊全力入魂」状態でした。「一冊の力で世の中を変えてやる」と力んでいたんですが、いまは「レーベル単位でメッセージを発していく」ことを軸に、数ある企画を〝集合体〟や〝生態系〟のように捉えることができるようになってきましたね。僕はこれから、コンセプトの時代になっていくと思っています。そのなかで「文脈」をつくることこそが、編集者の仕事になっていくんだろうな、と。ストーリーと言ってもいいかもしれません。ぶつ切りの1冊ではなく、「全体の活動自体」をメッセージとして伝えていかないと、もう消費者には届かないという、よりシビアな時代になると思いますよ。というか、もうなっていますね。「ベストセラー」にも、もうあまり意味はないんですよ。
Q:私はNHKの情報番組でディレクターの仕事をしています。私はいま、柿内さんが「一冊全力入魂」とおっしゃったことに近い番組づくりをしているのですが、さきほどのお話を聞いて、情報番組全体としてのレーベル感というかコンセプトが足りないのかなと思いました。で、質問ですが、「新書はコンセプトが大事」という発想に至るには、まわりに刺激し合う仲間の存在などがあったのでしょうか?(ジセダイ勉強会参加者)
柿内 出版業界というのは、敵対・競争しているように見えて、べつにあんまりライバル関係とかじゃないんですよね。ゆるやかに横でつながっていて、たとえば二社合同で同じ著者のフェアを書店で展開するということも、よくあります。じつは、このジセダイ勉強会で話をしているコルクの佐渡島庸平、spreeの安藤美冬、そして次回の話し手である東宝の川村元気も、みんな同世代の「仲間」ですね。もちろん、NHKの神原一光もです。
神原 20代のはじめの頃からみんなで定期的に集まって議論したりして、お互い刺激し合っているし、最近では一緒に組んで仕事もし出しましたね。
柿内 僕が思うのは、これからはもう一社ひとり勝ちのような時代ではないということです。担当作の一冊がベストセラーランキングに入ったとしても、それだけじゃ大きな流れはつくれません。「売れてよかったね」で終わりです。星海社新書が売れても、それだけではあまり意味はありません。そんななか、僕がこれからやっていきたいのは、出版業界全体で何か大きな流れ、「文脈」をつくっていくということですね。そのために、各社横断的なイベントや事業を、20代・30代の同世代編集者たちと手を組んでやっていきたいですね。これは大きな目標です。でも、そういうことをやるために星海社新書を創刊したんですね。
神原 なるほどなるほど。それは、たとえばロックフェスティバルみたいなものなんでしょうか? たしかに出版社でそういったものは、あまり見たことがありませんね。
柿内 そうなんですよ、意外なことにあまりないんです。出版業界全体でやっていることといえば、とにかく出版点数を増やして、ビジネスのラットレース化を加速させていくことくらいですから(苦笑)。みんな、どんどん忙しくなって、どんどん視点が短期的になってきています。僕らもそれに大きく加担しているので、忸怩たる思いがあります。だから、僕らの世代で、この流れを少しでも変えていきたいんですよ。
神原 最後に私から質問したいのですが、柿内君が就職活動中の学生に自分の仕事の良さをアピールするとしたら、どう説明しますか?
柿内 良い質問ですね。そうだなー、じつは最近、就職活動中の大学生とご飯を食べる機会があって、「出版業界ってどうよ?」って聞いたら、「斜陽産業で頑張っている残念な人たち」って言われたんですよね……。
(会場爆笑)
柿内 「空気読まないでストレートに言いやがって」と一瞬イラッとしたのですが、よくよく客観的に見たら、その通りだなと思いました。編集者って言われても、一般の人には本をつくっていること以上には何をしているのかがあんまり伝わらないんですよ。日本でいちばん有名な編集者は、「サザエさん」に出てくる伊佐坂先生の担当編集者であるノリスケさんだと思いますが、あんまり真面目に仕事していないでしょ?(笑) たまに「原稿もらいました」って感じで飲みに行くみたいな。
神原 ああ、ノリスケさんは、編集者でしたね!
柿内 出版社は放っておいても募集すれば応募がくるので、いまだに倍率は高いですし、危機感は薄いと思うのですが、それじゃ全然ダメです。僕は、本好きの人が出版社に来てもどうしようもないと思っています。最近は社会起業家やNPOに注目が集まっていますが、むしろ「世の中を変えていきたい!」という問題意識がある人にとって、出版業界が一つの選択肢にならないといけない。だってそうでしょ? すばらしい才能や思想を世の中に広めていくという仕事は、「世の中を変えていく」ことにつながらないはずがないわけですから。才能や思想をパブリックなものにするのが、パブリッシュ(出版)ですよ。だから、編集者は黒子でもいいのですが、自らの仕事や役割について、もっと外に向けて説明していく義務もあると思いますね。僕が「世の中を変えていきたい」という青臭い学生に出会ったら、「だったらこの業界に来いよ」と言いますね。
神原 そうですね。テレビでもまさに同じことが言えると思います。ぜひ問題意識のある学生たちと、一緒になって次のテレビを盛り上げて行きたいですね!本日は長時間にわたり、星海社新書の編集長である柿内芳文さんにたくさんのお話をしていただきました。最後は私も思わず熱くなってしまいましたが、今日は本当にありがとうございました!
柿内 こちらこそ、ありがとうございました!




![[過去の放送]「僕らの地域活性化作戦」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130330.jpg)
![[過去の放送]「僕らの復興論」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130309.jpg)
![[過去の放送]「格差を超えて僕らの新たな働き方」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130101.gif)
![[過去の放送]「僕らの国際関係論」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20120929.jpg)