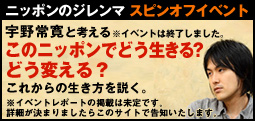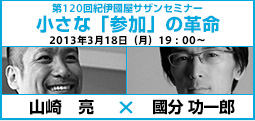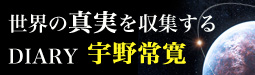「わざとらしさ」に意味がある : 「小さな参加の革命」(2/3) 山崎亮×國分功一郎
社会参加を考えるうえで要となる、住む人と地域の関わり合い。その貴重さや必要性は多く語られるものの、一方で「コミュニティ」「つながり」という言葉は、ともすれば敬遠されがちなことも事実です。当事者としての2人はかつて何を思い、そして今、何を考えるのか。コミュニティデザイナー・山崎亮さんと、哲学者・國分功一郎さんの白熱の対談「小さな参加の革命」第2回。見えてきたのは、「わざとらしさ」というキーワードでした。

「つながり」なんて胡散臭いと思っていた
國分 ランドスケープアーキテクトのローレンス・ハルプリンが、「優れたデザイナーは、住民の意見を聞けば聞くほどいいデザインを出せる」と言っているそうですね。山崎さんもいくつかのメソッドを使って、さまざまな意見の集積から、ひとつの完成されたデザインを、ある意味誘導するかたちで作っていくわけじゃないですか。これって、非常におもしろいなと思うんですよ。
山崎
僕ももともと設計を専門にしていたんですが、設計をやるときって、与えられた条件が全くないとすごくやりにくいんです。「予算は無尽蔵にあるから、どんなものを作ってくれてもいいんだ」と言われると、何を根拠にすればいいのか分からなってしまう。だからむしろ、与えられた条件の難しさをどう解くかっていうのが、けっこう燃えるところで。
ローレンス・ハルプリンの仕事を細かく見ていて気づいたのは、デザイナーと住民との間を調整する役割が必要なんじゃないかなということですね。デザイナーがいきなり住民の前に立って「意見をください」と言ったら、これは大変なことになってしまいます。だからコミュニティデザイナーとして働くうえでも、住民から出てくる100も200もある要望をいくつかのカテゴリーに分けて、いかにデザイナーが燃えるぐらいの条件にして提示できるかが燃えるところですね。
ハルプリンは非常に器用な人で、それを両方自分でやっちゃった人なんです。だけど、そのスタイルを真似るのは難しい。日本のデザイナーや建築家の多くは、ハルプリンのことは評価しながらも踏襲するのは難しいと思っている。
だったら自分はデザインをやめて、むしろデザイナーとの間をつなぐ役割のほうをやりましょうというところから、コミュニティデザインという仕事をやり始めるようになったわけです。
國分 でも、その「コミュニティ」という言葉を、昔はなにか、怪しいものだと思っていたとか。
山崎 胡散臭いなあと思ってましたねえ(笑)
國分 僕もわかるんですよ。僕と山崎さんは1973~1974年生まれで、ほぼ同世代ですから、同じ思想状況を経験してきていると思うんですが、学生の頃には「コミュニティなんて、何それ?」みたいな感じがなかったですか。
山崎 ありましたねえ。かっこ悪いですよね。「つながり」とか「絆」とかもそうですね。
國分 身体が痒くなる感じがしましたよ(笑)
山崎
僕は特に、ワークショップがすごく嫌いでした。わざとらしいじゃないですか。いい大人が、青色とか赤色とかの付箋に自分のアイデアを書いて。出したら、ファシリテーターと呼ばれる妙に笑顔の人間が出てきて「皆さん、このへん同じ意見ですよね」とか言うわけじゃないですか。「同じなわけねえだろ、いい大人が来て」とか、ずっと思ってました(笑)

國分 そう考えると、今ご自分がコミュニティデザイナーという肩書きで仕事をしているのって、不思議じゃないですか。
山崎
今は笑顔で「このへん一緒ですね」とかやってますからねえ(笑) 絶対「胡散臭い」と思われてるんだろうなと感じつつ。自分でやっていて恥ずかしいぐらいですよ。
でも、何度もそのわざとらしいワークショップの場に集まっている間に、参加者がすごくいい友達になっていることにも気がついたんです。ワークショップの後に飲みに行ったりしながら、本音でしゃべったり、悩みを打ち明けたりしている。
そういうことを経験していくと、その「わざとらしさ」はきっかけとして必要な気がしてきたんです。さらに参加している人は、すべて了解したうえで乗っているというか、演じているんだなということがわかってきて。その「大人の演じ方」の中に入らずに、若い奴が遠目で「あんなのかっこ悪い」と斜に構えているのは、逆にかっこ悪いことなんじゃないかと思うようになったんです。
人為的につくられてきたつながりの場
國分
僕も、「わざとらしい」というのは、重要なことだと思います。わざとらしさを認めるというのは、つまり何かを人為的に用意するのを恐れないということです。
久田邦明先生という地域社会研究をされている方からお聞きしたんですが、かつて日本の地域共同体を支えていた講や結、連なんかは、非常に人為的に作られていたそうですね。
たとえば「かつては老人が尊敬されていた」とか言われるけれど、それは老人たちが尊敬されるような知識の担い手だったからです。そして彼らがそうした知識の担い手になれたのは、若者たちが知らない知識を継承していくための場をきちんともっていたからだそうです。
老人たちは集まる場所をもっていて、そこで村人たちの悪口を言い合う(笑)。けれど、その外では決して悪口は言わない。さらにそうした場で、古老からいろいろな知識も伝達してもらう。そうやってつながりを作り、また知識を継承していく。すると、皆から「あのお爺ちゃんに聞けば何でもわかるよ」と思われる存在になっていく。
年寄りだからものをよく知っているなんてことはありえないんですよ。知識の継承の場が人為的に用意されていたからこそ、尊敬されるような知識人としての老人があり得たんですね。
山崎 そうですよねえ。
國分
子どもにしても、お祭りなんかの行事の中に、子どもだけで何かをする場が人為的に作られていた。僕らが小さい頃だったと思いますが、ある時から、ガキ大将がいなくなったって言われはじめたじゃないですか。あれも同じ問題として考えられる。
ガキ大将になる子どもは、子どもたちだけでやる行事のなかで何らかの主導的役割をあてがわれていた。そういう人為的な制度があったからこそ、ガキ大将のようなリーダーもあり得たし、つながりやコミュニティもあった。
古きよき地域共同体が自然に復活するということは考えにくいし、実際、人為的に作られてわけですよね。ならば、それにとってかわるものも、人為的に作らないといけない。その意味で「わざとらしさ」というのは大切な気がします。
山崎
まさにそうだと思います。その話、確かに聞いたことがありますね。
今の話に関連して言うと、どこかの集落で、毎年すごくでっかいシメジが採れる木があるらしいんですよ。でもその木の場所は、その村で尊敬されている1人の人間にしか伝えられない。つまり、集落の長老だけが知っているわけです。この人が、いよいよ自分の死期が近付いてきたなと思ったら誰かを呼んで、シメジの場所を教えるんですって。
まあ、シメジですから、形としてはかなり小規模ですが(笑)、今でもそういうことをやっている地域ってけっこうあるんですよ。それがGPSやなんかで誰もがわかっちゃうようになったら、その人はもう、尊敬されなくなってしまう。でも、そういうことが世の中にたくさん起きてしまっているのが今の時代でもある。
だから、國分さんの言うように「昔に戻ろう」というのは難しいと思います。だったらGPS時代の新しい仕組みとして、自分たちがある種のわざとらしさを持ちながら、形式としてつながっていく場を用意しておくのは、いいことなんじゃないかという気がしてきました。
誰も、ひとりでは生きられない
國分
僕らが大学生になったのって、92~93年ですよね。80年代が終わった頃って、「昔からのしがらみは全部ぶっこわした。これからは個人が屹立して、自由に生きなければならない」というテーゼが色濃くあった気がします。そして、「閉じられているものはダメで、開かれているものはよい」という、今考えればすごいイデオロギーがありましたよね。

山崎 ありましたねえ。
國分 これが間違っていたと思うんですよね。何もかもが開かれていて、そこに自立した個人が立っているなんて夢物語だと思うんです。なんだかんだ言って、つながりやよりどころがなければ生きていけない。そういう、よく考えれば誰でも分かる、すごく常識的なことに気づいてきたのが、この20年ぐらいなのかなあという気がします。
山崎
そうかもしれませんね。僕ら、言われましたよね。「誰にも頼らずに一人で生きていけるように、しっかり勉強して、いい会社に入りなさい」って。ずっと僕らはそう育てられたんですよね。僕らのちょっと上も下も、きっとそうだと思うんですよ。
でも、たとえば江戸時代の人たちって、子供を育てるときにそんなふうには育てなかったはずなんです。困っている人がいたら必ず助けなさい。あなたが困ったんだったら、必ず誰かに頼りなさいと。いわゆる「情けは人のためならず」ですね。人のために情けをかけるわけじゃなく、自分のために情けをかけなさいとずっと言われてきた。
これってつまり、「人とつながっていないと、あんたは生きていけないんだよ」ということを伝えてきたわけですよね。「一人で生きていけるように、知識や技術を高めなさい」という教育がされ始めたのは、そんなに昔のことではないような気がします。
その副作用が出てきたのもやはり最近のことで。そういう時代を生きたから、我々は教育なり社会のあり方を、もうちょっとよりよいかたちに変えていく必要があるのかなという気がします。
國分 「助けられなさい」ってすごくいいですね。助けてもらうって、けっこう大変なんですよね。自分でSOSを発しなきゃいけないし、身を委ねなきゃいけないところもあるし。
山崎
自分と関係が深い人には、逆に「助けて」と言いづらいそうですね。家族にだけはSOSが出せなかったり、職場の人には仕事の悩みを言えなかったり。逆に弱いつながりの方が「助けて」と言いやすいらしいんです。
『コミュニティデザインの時代』という本の中にも書いた小田川さんという海士町の女性は、30代で乳がんが発覚したそうなんですが、自分の病気を知ったときに感じた「何のために生まれてきたんだろう」とか、「明日から何もやる気がしない」という思いを、職場の人や家族にはどうしても言えなかったそうです。でも、海士町で一緒に活動していた15人のチームの人たちには、その赤裸々な悩みを打ち明けられた。彼らとは2週間とか、1カ月に1回しか会わないんですが、会えばおもしろい方法で励ましてくれたり、一緒に悩みに付き合ってくれたりして、だいぶ気持ちが蘇ってきたということを、後で伝えてくれたんですよ。
「つながりを作りましょう」と言うと、どうしても強いつながりを作るべきだとなりがちです。でも、「あってもなくてもいいけれど、あるね」くらいのつながりって、さまざまなことに効く可能性があるのを学びました。
だから、この弱いつながりをこの世の中にどう作っていくかが大事だという話を聞いたとき、まさに「コミュニティデザイン」という名前で僕らがやっているのは、そっちだなと思ったんです。

國分
なるほど。「弱いつながり」というのは、キーワードになる気がします。
僕は「保育」にすごく関心を持っているんですが、保育園がまちの中にあると弱いつながりがたくさんできるんですよ。先生やほかのお子さんの親と顔を合わせて、挨拶をしたりして。毎日顔を合わせていると、お互いのことを深く知っているわけではないのに、困ったときにちょっとお願いしたりすることが、けっこう簡単にできるんですよね。
僕には小学生の娘がいるんですが、保育園のときの父母のつながりはいまだに残っています。そういう意味でも、親がお迎えに行く場としての保育園も、弱いつながりを作るための1つの回路なのかなと思いました。
山崎
まさにそうだと思いますね。それってさらに「保育園のときのつながり」「小学校のときのつながり」というように、いろんなつながりが出てきますよね。
それと、それはいわゆる、地域の縁でつながるつながりですね。地縁型のコミュニティと言われるもので、同じ地域に住んでいるからこそつながろう、というタイプです。
一方、同じ趣味があるから集まるという人たちがいますね。鉄道が好きとか、お酒が好きというコミュニティですね。こっちはテーマ型のコミュニティと言われていて、別に同じ地域に住んでいるわけではないけれど、つながりができるわけです。
この2つのバランスをうまく使いながら、いかにその弱いつながりを作っていくかというのは、今の時代だからこそやらなければいけないことなのかもしれません。今、地縁型コミュニティの力がとにかく弱まりつつある。このあたりを、一体どんなタイプのコミュニティが補完していくのか。
そういう意味では、保育園のお迎えのときに会う人たちなんかは、地縁型ではあるけれど、その部分に該当する気がしますね。そうしたつながりは、とても大事だと思います。


![[過去の放送]「僕らの地域活性化作戦」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130330.jpg)
![[過去の放送]「僕らの復興論」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130309.jpg)
![[過去の放送]「格差を超えて僕らの新たな働き方」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130101.gif)
![[過去の放送]「僕らの国際関係論」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20120929.jpg)