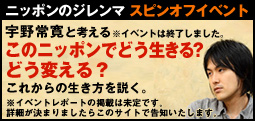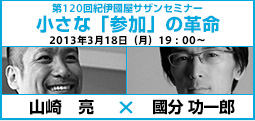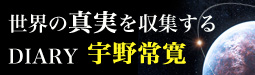新刊『ウェブ社会のゆくえ――〈多孔化〉した現実のなかで』:鈴木謙介
社会学者・鈴木謙介さんの新刊『ウェブ社会のゆくえ――〈多孔化〉した現実のなかで』が、本日2013年8月29日に発売となりました。スマートフォン全盛の今日、情報技術が現実空間を侵食する〈多孔化〉はますます進んでいます。ソーシャルメディアは分断をもたらすのか? ウェブ社会はつながりを取り戻すことができるのか? ソーシャルメディア疲れが進む若者の姿から、東日本大震災後の共同性の危機まで、〈多孔化〉した現実のゆくえを探る、待望の書き下ろしです。
本書の目次はこちら(※PDFファイルが開きます)で見ることができます。また、「はじめに(抜粋)」が以下からご覧いただけます。
● はじめに(抜粋)
現実とウェブが融合する時代
(……)
結局のところ私がこの本で論じたいのは、ウェブは既に(というよりも始めから)現実空間と区別の付かないものになっており、それゆえ、ウェブで起きていることだけを独立して論じたり、あるいは現実はウェブよりも重要で優先されるべきものであるという前提に立って議論したりすることが、もはや無意味になっているということだ。
ほんの少し前まで、ウェブにアクセスするといえば固定されたパソコンの前に座り、画面を見続けることを指していた。一日中ウェブに耽溺しているひきこもりのオタク、という明らかな偏見を含むイメージが受け入れられやすかったのも、デスクトップパソコンが自室に置かれ、それを見ている間は他の人と現実空間で交流することがないという物理的な制約を前提にしていたからだろう。
だがいまや、むしろテレビに近いと言えるこのようなイメージは過去のものになりつつある。特にスマートフォンの登場と普及、それと並行して進んだ高速ワイヤレス回線への移行によって、ウェブは自室のパソコンからではなく、手の中の小さな端末からアクセスするものになった。そしてそのことによって私たちは、バーチャルとリアルの対立ではなく、目の前の現実と、画面の中にあるもうひとつの現実との間にどう折り合いを付けるべきかについて悩まなければならなくなった。
たとえば友人との会話の場面。私たちは相手とお茶を飲みながら話している場面で、スマートフォンからソーシャルメディアにアクセスして、別の友人の近況を知り、また仕事のメールを受信することがある。フェイスブックなどのソーシャルメディア上でつながっている人は現実の世界でも面識がある人が多数であるというのが一般的である。つまり、画面の中の関係だからといって「にせもの」の関係であるとは言えない。だからこそ目の前の友だちを放っておいてソーシャルメディアで友だちに返信するわけだが、対面の人間関係がバーチャル世界の関係に優先するという規範は、そこではもはやお互いに期待されていない。
あるいはツイッターで流れてきたニュースから、すぐ近くにあるCDショップでお気に入りのアーティストがイベントを開催していることを知ることもあるだろう。かつてであればそのお店に入ったり、前を通りがかったりしなければ気付かれることのなかった「現実」が、ウェブを通して知られるものになるとき、ウェブの情報の質は現実よりも劣るという想定を立てることはもはや不可能である。
このように、現実空間の中にウェブが入り込み、ウェブが現実で起きていることの情報で埋め尽くされるようになると、かつて「現実の空間」だと思われていた場所に、複数の情報が出入りし、複雑なリアリティを形成していることに気付く。本書ではこうした、現実空間に情報の出入りする穴がいくつも開いている状態のことを「現実の多孔化」と呼んでいる。現実が多孔化し、またそれを通して様々な人の思惑がばらばらに入り込んでくるようになるとき、私たちは「この現実」における他者との共生関係をどのように維持すべきか。それが本書の課題だ。
その課題は大きくふたつに分けられる。ひとつは、リアルとバーチャルの優先順位が混乱し、ときにリアルの方がないがしろにされるときに、親密な他者との関係のあり方や考え方に変化が生じるということだ。たとえば恋人とのデートの最中に、頻繁にソーシャルメディアにアクセスするという振る舞いを快く思う人はあまりいないかもしれない。ではたびたびスカイプのビデオチャットで孫の様子を見て喜んでいる祖父母の場合はどうだろう。遠方で、あまり実家に帰ってこない子や孫と、映像とはいえ触れ合う機会が増えることを問題だと考える人は少ないのではないか。
しかしながら、ここには「親密さ」をめぐる大きな考え方の変化がある。これほどまでにパーソナルメディアが個人の間に入り込んでくる以前には、親密さとはある程度、物理的な距離の近さと関連付けて捉えられていた。ソーシャルメディアのような手段の普及は「物理的な距離が近いこと」と「心の距離が近いこと」の関係を、あいまいなものにしてしまう。
もうひとつの課題は、物理的な距離の近さと親しさの関係が不明瞭になると、ある空間の中に生きる人々が、ある「社会」の中に生きているという感覚もまた、確かさを欠くものになるのではないかということだ。近代社会はその特性上、互いに見知らぬ人々が同じ前提を共有して生きていくことで維持されてきた。そしてその前提は、過去から未来へと受け継がれるものでもあるため、公的な空間におけるセレモニーや式典などの行事が重要な意味を持っていたのだが、物理空間に情報空間の関係性が入り込んでくるようになると、そうした公的行事の意義もまた薄れてしまう。
本書は、このような「空間」と「情報」をめぐる様々なレベルでの葛藤や対立を、主として社会学の視点から描き、理解することを目的としている。ただし、私自身は現実の空間にウェブ上のコミュニケーションが入り込んでくることに対してやや批判的だが、そうした「礼儀知らず」な振る舞いにどうやってお説教をすればよいか、というようなことは、本書では扱っていない。むしろそうした日常的な出来事と、社会全体で扱うべき問題の間に同じ原理があって、両者はともにつながっていることを示そうと試みている。
特に本書は、前半において、現実空間に開いた穴から他の場所の情報やコミュニケーションが入り込み、それらと現実空間の出来事の優先順位が混乱するという「多孔化」の問題を、後半においては現実空間が多孔化することによって、同じ空間、同じ社会を生きる人々の関係が変化し、これまで社会を維持するために用いられてきたいくつかのメカニズムが機能不全に陥る可能性を提示している。
(……)
このようなテーマを扱った本が書かれた背景について述べておきたい。本書は、ウェブと現実との連動が進むひとつの例として、主にAR(Augmented Reality=拡張現実)の技術動向について社会学の視点から分析する本として、二〇一〇年頃に構想が始まった。だがその後、東日本大震災が発生し、また技術的・社会的な動向が変化する中で、より抽象度の高い視点から、普遍的なテーマを設定する必要に迫られ、大きく構想を練り直した。
というのも、そもそも当初の段階で考えられていた「現実空間の情報化が進むことで、人々の間がますます分断されていく」という問題設定が、非常に重い意味を持つようになったからだ。
東日本大震災のおり、被害という意味ではそれほどではなかった首都圏でも、交通機関がストップし、大量の帰宅困難者が発生し、タクシーを待つ行列ができた。スマートフォンでソーシャルメディアにアクセスできた一部の人は、首都圏の交通がマヒしていることを知り、その列を離れて自力で帰宅する道を選んだが、いつまでもそこで来ないタクシーを待ち続けた高齢者もいたという。誰かがそこで「待っていてもタクシーは来ないですよ」と声をかけることがなければ、両者は同じ空間を生きていたとしても、同じ社会に生きているとは言えない。
私たちの社会が自由を重んじる以上、そのような差が生まれることを咎め立てする理由はないのかもしれない。だが、震災とそれにともなう種々の被害は、私たちにひとつの課題を投げかけたはずだ。すなわち、その場所がどのような場所で、どのくらいのリスクを抱えていて、かつてどのような被害を受けたのかということを、私たちが忘れないようにしなければならないという課題を。
放っておくと、災害や事故の記憶というものは、当事者以外の人々の間から消え去り、受け継がれることもなくなり、ただ風化していってしまう。そして情報化された空間を個人的に生きることができるようになることで、空間の意味が変質するだけでなく、それを他者と共有することができなくなってしまう。放射能汚染の問題のように、最低でも数十年の単位で考えなければならないことがある一方で、私の住んでいる神戸では、阪神淡路大震災の記憶を継承することにすら困難を感じる場面が存在する。
そこで本書では、空間の情報化がそのような社会の分断を招く一方で、その特性を活かして多様な人々の間を取り結ぶような「情報」で、意味的に分断される空間をハッキングするという課題に挑戦することになった。それに成功できたかは心もとないが、少なくとも目の前の明確な課題に対応することだけが、いま考えなければならないことだという風潮に対する問いかけにはなったのではないかと考えている。こうした抽象度の高い問いが必要とされなくなるとき、震災後に生じた様々な課題もまた、現時点では現実的なように見えて、結局は場あたり的なものにしかならない対処を導くだけになるのではないか。本書を貫いているのは、そうした懸念だ。
(……)


![[過去の放送]「僕らの地域活性化作戦」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130330.jpg)
![[過去の放送]「僕らの復興論」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130309.jpg)
![[過去の放送]「格差を超えて僕らの新たな働き方」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20130101.gif)
![[過去の放送]「僕らの国際関係論」出演者に聞いてみた!!](/shared/images/common/r_bnr_tv_20120929.jpg)